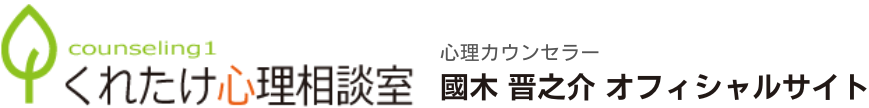HSPとは?日常の刺激に敏感なあなたへ|気質との付き合い方と自分らしさについて
HSP(ハイリー・センシティブ・パーソン/Highly Sensitive Person)という言葉をご存知でしょうか。
アメリカの心理学者エレイン・N・アーロンが90年代に提唱した概念で、「感受性が強く、敏感な人」を指します。
日本でも広まりを見せ、多くの人が「もしかして自分もそうかもしれない」と感じるきっかけになっています。
このページでは、HSPの代表的な特徴や、HSP的な気質とうまく付き合うための工夫に触れつつ、こうした言葉との付き合い方についてまとめます。
HSPとは
HSPは病気や発達障害ではなく、生まれ持った気質のひとつとされています。
全人口のおよそ15〜20%が当てはまるとも言われ、敏感さによって人の気持ちを察したり物事を深く考えられる一方で、刺激に疲れやすいこともあるとされています。
HSPの特徴
HSPの特徴としては、次のようなものがよく紹介されています。
- 物事を深く考えて行動する
- 刺激を過剰に受けやすい
- 共感しやすい
- 小さな変化に気づきやすい
こうした傾向は誰にでも多少は見られますが、特に強く表れる人は「HSP的な気質を持つ」とされています。
HSP的な気質とうまく付き合うための工夫
HSP的な傾向がある場合、次のような工夫が役立つとされています。
- 刺激を受けやすい人や物事と距離を取る
- 一人で休める時間を意識的に確保する
- 自分がリラックスできる方法を知っておき、定期的に実行する
- 相手の感情をネガティブに想像したときは、必要に応じて言葉で確かめる
この他にも、HSPについて知り、自分が心地よく生きるための工夫を少しずつ取り入れていくことが大切だとされています。
こうした言葉との向き合い方
HSPという言葉に出会い、「自分の感覚に名前がついた」と安心したり、「同じような人がいる」と知って孤独感が和らぐ人も少なくありません。
そうした安心感はとても大切なもので、多くの人の心の支えになっています。
一方で、HSPという言葉が広まったことで、「私はHSPだから」とアピールするように使われてしまう場面もあり、そこに違和感やしんどさを覚える人もいます。
また、「自分はHSPだからこうなんだ」と考えを狭めてしまう危うさも指摘されています。
刺激に敏感であるという気質の背景には、生育環境や発達特性、あるいは心身の不調など別の要因が関わっている場合もあり、HSPという言葉だけでは説明し切れないこともあります。
そうした要因が見えにくくなり、本来必要なサポートに辿り着けないケースもあります。
HSPに限らず、こうした言葉はあくまでも「自分を知るためのきっかけ」として有効に活用しつつ、それに縛られすぎないことが大切かもしれません。
カウンセリングにできること
カウンセリングでは、「あなたが今どんなことに困っているか」を出発点として、一緒に考えていきます。
HSPはマイノリティであるぶん共感されにくいこともあり、安心して話せる場で自分の気持ちを言えただけでも気持ちが軽くなることがあります。
そうした場で話すうちに、HSP的な気質が関わっているとわかることもあれば、別の要因が見えてくることも、複数の要素が絡み合っていると気づくこともあります。
原因をひとつに決めつけず、いくつかの視点を持ちながら、「HSPの人に合った方法」ではなく「あなたに合った方法」を探していきます。
おわりに
HSPに限らず、自分の特徴や傾向を知り、それをどう扱うかを考えることは、生きづらさを和らげ、より自分を活かすことにつながります。
HSPのような言葉を有効に活用しつつ、その先にある「自分らしさ」を探っていくことが、あなたらしく生きるきっかけになるかもしれません。
ご利用のご案内
直近の空き状況は 予約カレンダー からご確認いただけます。ご不明な点がある方や、「こういう悩みでも大丈夫か確認したい」「受け方を相談したい」という方は、お気軽に お問い合わせフォーム からご連絡ください。